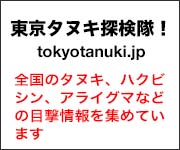東京コウモリ探検隊! 探索録
2025年05月03日の巻
2025年05月03日(土)
今回のアブラコウモリ探索は荒川の前回からの続き。
今日はバスで荒川に向かうことにする。
「赤31」バス。高円寺から出発し、終点は赤羽駅東口。環七通りをひたすら北上し、約35分。東京都23区では最長路線ではないが、けっこう長い方の路線のはずである。23区最長路線は「王78」(新宿駅西口~王子駅前)だが、経路がそれとほぼ重なっている。
東京都心はだいたい電車でなんとかなるものだが、バスの方が小回りがきく場合もある。今回も赤羽に行くなら乗り換えなしで行けるバスの方が楽である。
バスでは一番後ろの右側に座る。窓が大きく、外の風景を楽しめる席だ。見えるのは昔ながらの風景。前回乗ったのはいつだったか忘れたが、いつもの変わらない眺め。後半になって気づいたのは、電線地中化がまだの区間があることだった。幹線の地中化はかなり進んでいると思ったが、ここはまだだったか…。他の場所でも注意して見ておこう。
赤羽駅東口、到着。日没にはまだ時間があるが、新河岸川に着く頃に日没になるだろう。
北に向かって行くと、赤羽岩淵駅からぞろぞろと人が南に移動してきた。服装からすると、サッカー観戦の帰りか…。乗り換えでJR赤羽駅に向かっているのか。
新河岸川へ近づきつつあったところで、後ろから消防のバンがサイレンを鳴らして追い抜いていった。新河岸川沿いの道路でもサイレンを鳴らした別の車が通りすぎて行った。
前回アブラコウモリを観察できた岩淵八雲神社の前に来たところで、バットディテクターから音が聞こえる。見上げると神社前の駐車場上空をアブラコウモリが飛んでいる! まだ日没前なのに!
その先の岩渕橋でもアブラコウモリを確認できた。こちらもまだ日没前。下流の新志茂橋に消防車両が集結しているのが見える。火事か、事故か。
新河岸川沿いに下って行く。(そうするうちに日没時刻を過ぎた。)
今度は新志茂橋を消防車両が渡って行く…。現地の方はご存じだろうが、この橋は普通は車は通らない。何があったのだ。
こちらは歩いているうちに多数のアブラコウモリを発見した。荒川知水資料館アモアの前。新志茂橋のたもとである。目視だけでも6頭を確認できた。虫がたくさん飛んでいるということだろう。
堤防に上り、下流へ進んで行くと前回のゴール、青水門である。が、前回と違い、消防&警察車両が5台ほど集結している。訓練ではない。酸素ボンベらしいものも置かれている。青水門から見ると、緑地の突端で何かをしているようだ。
後でネット検索してみたが、何をしていたかはわからずじまい。

写真にも赤色灯が写っている。上空には月。
ここからが今日の探索のメイン行程になる。ヘリポート脇を通り、荒川堤防に下りて行く。新河岸川でも気づいていたが、風が強い。寒い。19℃。前回の探索終了時が20℃だったので、もうそれより寒い。が、アブラコウモリはちゃんと飛んでいるので問題ない。ただ、低温は好ましくはない。気温が下がりすぎなければよいが。
河川敷に下りるとそこは新東京都民ゴルフ場である。このコースは歴史あるゴルフ場らしいが、今は9ホールだけである(当初は36ホールもあった)。前回の赤羽ゴルフ倶楽部と同じく2019年の台風で土砂が流入し、翌年夏まで営業できなかった。河川敷ゴルフ場の宿命とはいえ大変なことである。2019年以降は幸い台風による増水はなかったが、これはたまたまのことで、いつまた増水してもおかしくはない。
ということを考えていると、メッシュの境界線を通りすぎていることに気づいた。メッシュとは、3次メッシュのこと。より正しくは「標準地域メッシュの第3次メッシュ」というべきか。簡単にいうと、日本全国を約1km四方に区切る網(メッシュ)である。各種の地理的な統計は標準地域メッシュで区切られており、東京コウモリ探検隊!では、そして東京タヌキ探検隊!でも利用している。そのため、メッシュ境界を把握しておくことは重要である。(メッシュは緯度経度で区切られるので正確な1kmではない。しかし計測誤差が生じにくい確実な区切り方だ。)
ここはちょうど縦横の境界線が交差するところである。なので少し戻って再確認することにした。ついでに堤防の上に上る。堤防の反対側はすぐ新河岸川である。風はまだ強い。薄手のパーカーを着ることにする。持ってきて良かった。気温18℃。
ところで、地図を見るとわかるのだが、この辺りは「埼玉県」だったりする。かつての流路の名残なのだろうが、東京都側に埼玉県がくい込んでいるのだ。前回のルートでも埼玉県の侵食エリアはあった。実際は東京都が管理しているのだろうが、整理はできないのだろうか。
少し下流へ行ったところで荒川河川敷に下りる。ところでクビキリギスは今日も鳴いている。ただし前回ほど迷惑ではない。今日のルートは草むらが少なく、クビキリギスが少ない。
風はおだやかになってきた。
ゴルフ場が終わり、鹿浜橋の少し手前でネコ1頭と遭遇した。ようやく見つけた。だが、今回遭遇したネコはこの1頭だけだった。
鹿浜橋の下流は新田わくわく水辺広場である。中央は池、干潟、ワンドがあり、タヌキがいるんじゃないかと思いたくなる場所である。実際はよくわからない。
ここにも水辺に面して観察デッキがあるが、そこにはアブラコウモリはいなかった。ただし、近くではアブラコウモリを観察できた。
水辺エリアを通過し、広場に入って行くと、「ゲ、ゲ、ゲ、ゲ、…」と鳴き声が聞こえてきた。カエルだよな…? しかも舗装路の方から聞こえてくる。草が生えているところにいるなら見つけるのは難しいだろう、とわかってはいたが、念のため確認してみることにする。見たところ草丈はとても短く、カエルが隠れるには不向きそうだ。舗装路に足を踏み出すといきなり足下で大声で「ゲ、ゲ、ゲ、ゲ、…」と鳴き始めた。びっくりしたあ。

iPhoneのライトをつけて探すと小さなカエルが3頭。ニホンアマガエルか。いや、今はヒガシニホンアマガエルか(今年、新種となった)。近くには他にも何頭か鳴き声が聞こえる。いきなり新種に対面というのはめったに体験できることではない。昔々からそこにいるカエルだとしても、ね。新種だと思って見るといろいろとなんだか感慨深いような気分になる。大発見をしたような気分を少し味わえる。
ところで東京都23区のアマガエル、確かに前にもどこかで鳴き声を聞いたことはあるがどこだったたか。東京都23区にカエルがいることが信じられないという人はいるだろうが、それは偏見である。ちなみに東京都23区で最も繁栄しているカエルはアズマヒキガエルである。
さて、ここのアマガエル、ちょっとまずいのではないか? この道路は夜も自転車やランナーが走っている。散歩の人もいる。河川敷には照明はなく、真っ暗。これで体長数cmの物体を見つけるのは不可能だろう。これまでもアマガエルは踏みつけられてきたに違いない。気をつけましょう、と言ってもこれは無理だ…。
先に進むと、前方の草が茂っているところからもアマガエルの鳴き声が聞こえる。
豊島五丁目グリーンスポーツ広場の手前でもアブラコウモリを確認。だが、アブラコウモリを確認できたのはここまでだった。時刻は20時を過ぎたところ。日没からまだ1時間30分ほどである。

豊島五丁目グリーンスポーツ広場はGoogleマップでは未整地なのだが、今、目の前にはきれいな陸上トラックとラグビー場がある。最近できたのだろう。
その脇の舗装路だが、路面がぬれている。堤防から水がしみ出しているように見える。前日が雨だったことも関係あるのだろうか。この光景、前にも見たことがあったな。
五色桜大橋は光っていた。中央のアーチがライトアップしているのだ。この橋は首都高速道路で、2段重ねという大きな橋である。
その次の江北橋を過ぎると、また舗装路が水びたしである。ここは覚えているぞ、前回も水びたしだった。前回とは2017年。
探索は続くが、アブラコウモリは現れない。
気温は18℃。さっきのアマガエルの辺りでは17℃だった。17℃はさすがに寒い。アブラコウモリの活動限界気温は15℃だが15℃になったらぴったり活動をやめるのではなく、気温が下がるにつれ活動量は減っていく。17℃では活動をやめる個体も多いだろう。気温は日の出時刻まで下がる一方、上がることはない。ならばアブラコウモリの活動も戻らないだろう。ということは、今日はこれ以上アブラコウモリは見つからなさそうだ。今日は北千住まで行きたかったがきっぱりあきらめるのも必要だ。なのだがどうやって帰ればいい? 地元の方々も苦労されているだろうがここは交通が不便だ。近くに駅がない。一番近いのは日暮里・舎人ライナー(面倒なので以下、日暮里省略)なのか。もう少し先だ。
扇大橋手前には大量の土が積み上げられている。まさか2019年台風の時の土砂を積んでいるのか?
扇大橋は舎人ライナーも通っており、ここで今日の探索は終了とする。
舎人ライナーの高架線路はかなり高い。改札は堤防と同じ高さにあるのでそれほど高く感じないが、その改札階は堤防下から見ると数階の高さにある。舎人ライナーは荒川北岸では高速道路を乗り越えていて、かなりの高さだ。舎人ライナーは全体に高架が高いのだが、ここは特に高い。建設順では高速道路の方が早いので、後からできた舎人ライナーはその上を通らざるをえない。かなり無理してるよね。
今日のアブラコウモリ探索は終了。あさってにも続きをしたいが、さてどこから再開するか。
日没時刻 18時29分
観察箇所数 20
歩行距離 8.0km
歩行時間 約2時間30分
気温 21℃→18℃
筆了2025年05月05日(月)