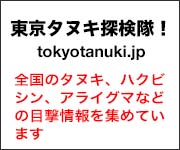東京コウモリ探検隊! 探索録
2025年07月14日の巻
2025年07月14日(月)
台風5号が東海上を通過…というのが昼間の状況。予報では夜は雨は降らなさそうなのでアブラコウモリ探索に行くことにするが風は強いかも…。予定では海岸地帯に行くつもりだったのだが、海岸や河川は強風の影響を受けやすい。多少の風でもアブラコウモリは活動するが、より良い条件で観察はしたい。そうなると別の候補場所を探さねばならない。海や川でない場所、できれば江東区で、となると、、がいいか。水路はあるが大きなものではないので風の影響は少ないだろうと期待した。今日は念のため折りたたみ傘も持って行く。
19時過ぎ、メトロ東西線、木場駅到着。まずはすぐ南のを経由し、洲崎神社へ向かう。洲崎神社は奇妙な神社である。拝殿が西を向いているのである。それのどこが奇妙なのかと思われるかもしれない。東京都区部の神社はほとんどが拝殿は南向きか東向きだからである。それ以外の向きはとても少ない。全国的に見ると南向き東向きは多いだろうが、それ以外の方向も珍しくはない。宮本隊長は福岡市生まれ育ちだが、北向きの神社は普通にある。東向き、というのは日の出の方向を向いているとわかる。南向きは東京都区部の場合、海を向いているということだ。福岡市の北向き神社も海を向いているのである。
洲崎神社の向きは成り立ちに関係していると考えられる。洲崎神社は江戸時代は島だった。今では埋立地に囲まれてしまっているので島の名残はない。江戸から参拝に行くには船に乗るしかない。その船着き場は江戸に近い島の西側だったのだろう。そこから参道がのびていたとすれば拝殿は西向きになるということである。
洲崎神社に参拝。脇の稲荷様、弁天様にも参拝。宮本隊長にとっては小さな神様たちも大切なのだ。
洲崎神社のすぐ北にあるのが新田橋という歩行者用の小さな橋。橋の上から見上げると、台風の影響か雲が南から北へと急速に流れているのがわかる。時折、川の上を強い風が走り抜けていく。だが常に強風ということではない。
大横川に沿って上流に向かい、木場公園に入る。木場公園では南半分を反時計回りに1周する。樹木が多いのであちこちでアブラコウモリを確認できる。途中にあるプールは泳いだり水遊びのためのものではないことは見ればわかる。このプールは角乗(かくのり)で使っているらしい。角乗とは水に浮かべた材木を操り、いろいろな演技(曲芸)を披露するというもの。「木場」とは貯木場のこと。昭和まではここは貯木場だったのだ。角乗は材木を操る技術だった。
木場公園を出て東に向かうと横十間川親水公園。名前からも、そしてずっと細長い公園が続いていることからもわかる通り、元は川、というより人工の運河だった場所である。今も形ばかりの水路は残っている。道路と交差している場所はかつては橋だったが今はその痕跡もない。公園が北に折れ曲がり、少し進むと仙台堀川公園に出る。その合流地点には小島があるのだがそこはサギのねぐらになっている。暗くて少し距離があるのではっきりと確認できないがコサギが20頭以上はいるようだ。おそらく繁殖もしているのではないだろうか。それよりもこの辺りではムクドリのうるさく鳴いている。樹木がムクドリの集団ねぐらになっている。やはり暗くてムクドリの姿は確認できない。
仙台堀川公園は東方向へは細い水路になっている。横十間川親水公園と違い、こちらの道路は今も橋らしい姿を残している。公園の遊歩道は橋の下をくぐっているので車を気にせずに往来できる。進んでいくと、ちょっと奇妙な橋がある。車道ではない橋…これはJR貨物線の線路である。JR亀戸駅から南へ枝分かれしている貨物専用線で、塩浜の越中島貨物駅までつながっている。運行本数はかなり少ない。この鉄橋の下は水路になっているのだが、水位が高いせいか浮橋になっている。仙台堀川公園は細い水路があるおかげかアブラコウモリは所々で確認できている。
仙台堀川公園が90度北へ向きを変える所で公園からいったん出る。南へ進み、トピレックプラザという商業施設を抜けて、まず南砂三丁目公園へ。ここは特別な場所ではないが当分来ることもなさそうなので行ってみることにした。アブラコウモリは確認。ここは必ずいそうな場所である。
次は東へ向かう。前回、荒川河川敷でアブラコウモリを確認できなかったメッシュである。河川敷まで行く時間はない。しかしこの辺りには大きな公園、緑地は無い。こういう場合は学校を目指すのが策である。学校にはたいてい高木が何本も植えられており、そこにアブラコウモリが来ることがあるからだ。地図を見るとちょうど小学校と中学校が並んでいるではないか。現地に到着すると学校の間の道路でアブラコウモリを確認できた。これで寄り道の目的は達成したので元のルートに戻ることにする。
仙台堀川公園に戻るとすぐに旧大石家住宅がある。見た目はただの古民家で何かすごいものには見えないが…「江東区内に現存する最古の民家住宅」とのことで、江戸時代、1855年の安政の大地震の前に建てられたと説明されている。すごいことはわかったが、私にとってはあまり感動するほどのものではない。残念ながら。
そのすぐ先には区民農園がある。…が、Googleマップでは違うものが表示されているぞ。これは釣り堀か。そういえばそうだったか。ということは区民農園は新しいのか。後で調べると今年5月にオープンしたばかり。もういろいろな作物が成長しているようだった。
ここからの仙台堀川公園はアブラコウモリがなかなか確認できない。細い水路はあるがほとんど水がない。橋らしい橋もなくなっている。樹木はあるのだからアブラコウモリはいるはずなのだが。そこで仙台堀川公園の脇にある公園にも立ち寄ることにする。まず城東公園。ここはいわゆる交通公園で、貸出自転車で交通ルールが学べる施設。アブラコウモリはいない。
さらに北へ進んで次は亀高公園。こちらではアブラコウモリが確認できた。隣接する小学校のプールの上を飛んでいるようだ。学校のプールもアブラコウモリがよく来る場所。なので探索ではやはり学校は重要な場所だ。なお、プールの水はきれいでも汚くても関係なくアブラコウモリは来る。水があれば来る昆虫もいるのだろうと推測している。それをアブラコウモリが食べに来るのだ。

そして小名木川に到達。ここが今日のゴールである。小名木川にはまた来ることになる予定。空を見上げると雲はまだ南から北へと流れている。この雲の動きは木曜まで続いていた。東京ではそれほどでもなかったが、静岡の方では雨や突風で大変なようだった。
ここから一番近い駅は都営新宿線の大島駅か…。歩いて10分はかからない。途中、持参の温度計を見ると湿度が80%になっていた。道理で蒸し暑かったわけだ。翌日、気象庁のデータを見るとこの時間帯、確かに湿度は80%オーバーだった。

写真は大島駅の出入り口の表示。「-2.2m」の表示にギョッとするかもしれない。これがつまり「海抜ゼロメートル地帯」でこの辺りはどこも0m以下である。東京都23区の最低標高を調べたことはなかったが、ここがどん底、という地点ははっきりとしない。そもそも地形がほぼ平らで、窪地があるわけでもないので特定は難しいだろう。標高が表示されている場所ならば、どうやらこの大島駅の出入り口が最低標高となりそうだ。実際には-3mの地点はあるようなので、標高の表示場所があるならば教えてほしい。
今日もよく歩いた。
翌日の夜は雨。台風当日に雨が降らないのは幸運だった。1日違いで探索に行けたり行けなかったりする偶然頼みなので細かい予定を立てても意味がない。天気予報には注意していても直前まで雨を予測できないこともある。スマホで雨雲の動きが見える時代でも予報は難しい。
梅雨はまだ明けていない。
日没時刻 18時58分
観察箇所数 27
歩行距離 11.6km
歩行時間 約3時間30分
気温 28℃→28℃
筆了2025年07月23日